 対象疾患の現状 対象疾患の現状
骨関節疾患とは、骨や関節など骨格に病変を有する疾患です。1998年度国民生活基礎調査によると、そういった筋や骨格などの病変に由来する訴えを有する患者さんは、約3000万人に達するとされます。内訳としては、腰痛が1160万人、肩こり1140万人、手足の関節の痛みが680万人となっています。疾患別でみると、変形性膝関節症が1200万人、骨粗鬆症が600〜700万人、関節リウマチは70万人などと推定されています。人口の高齢化の影響もあり、これらの疾患に対する対応が重要となっています。治療には薬物療法や手術療法とあわせてリハビリテーションが必要となることが多くなっています。
診断からリハビリテーションへの流れ
ひとくちに骨関節疾患といっても上記のようにさまざまです。まず、適切な診断をもとに治療方針を決定し、その後リハビリテーションを行います。リハビリテーションでは、理学療法・物理療法・装具療法・生活指導などを行い、あわせて介護保険制度の利用(家屋改修・ヘルパー利用)など、生活環境の改善をめざします。
今回は、リハビリテーション科で治療を受けることが多い疾患の中から、腰痛症、頸部痛、大腿骨頸部骨折、変形性関節症、骨粗鬆症について話を進めます。なお、関節リウマチについては、関節リウマチのリハビリテーションをご参照ください。
腰痛症
腰痛症のリハビリテーションは、腰痛体操・運動療法の指導や、物理療法(温熱・寒冷療法、牽引など)、装具療法としてのコルセット作製などがあります。腰痛へのアプローチで最も重要とされるのはその予防で、有効な予防法の研究が行われています。
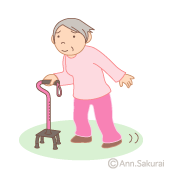 頸部痛 頸部痛
頸部痛は、首周りの痛みだけの場合と肩周囲の運動制限が伴うことがあります。リハビリテーションは、頸部周囲をリラックスさせたり、筋肉のマッサージ・ストレッチなどの理学療法を行います。あわせて物理療法(温熱・寒冷療法、牽引など)を行う場合もあります。前項の腰痛症にも当てはまりますが、生活指導を受けることが悪化・再発を防ぐことにもなります。
大腿骨頸部骨折
骨折を起こした際には、入院して手術が行われるのが一般的です。その後のリハビリテーションとして、筋力トレーニング、歩行訓練や起居動作訓練を行います。手術をしない場合も期間は異なりますが同様に行います。退院前には転倒予防などを意識した環境面の調整や、機能維持のためのホームプログラム指導などを行います。
変形性関節症
各関節の変形による病気で、多くは痛みを伴います。リハビリテーションでは、関節に痛みを出さない状態での筋力強化訓練などの運動療法、鎮痛を目的とした温熱・寒冷療法などの物理療法、装具処方による関節保護を行います。慢性的な疾患ですので、関節症状を悪化させないための生活指導や自主トレーニング指導が必要となります。
骨粗鬆症
骨粗鬆症では、未治療では骨折等に進行するおそれがあり、骨折の予防としても、リハビリテーションが重要となります。リハビリテーションとしては、骨の強さと歩行能力などを維持・改善する目的で運動療法を行い、日常生活で続けられるような運動を指導します。また、症状にあわせて物理療法・装具処方を行います。 |