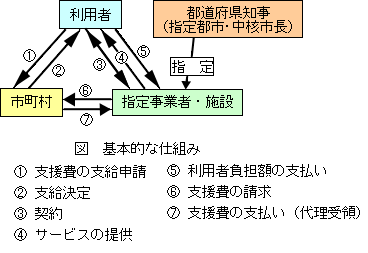
支援費制度について
今年4月1日から障害者福祉サービス提供の仕組みが変わり,支援費制度がスタートします.以下に,この制度のアウトラインを述べます.
1. 支援費制度が目指すもの
全く新しい制度ができるのではなく,行政がサービスの受け手を特定し,サービスの内容を決定するという措置制度から支援費制度に移行いたします.支援費制度とは障害者の自己決定および利用者本位のサービス提供を尊重する制度です.障害者自ら事業者・施設との対等な立場で,サービスを選択し,契約する仕組みになります.
利用者は事業者・施設からサービスの提供を受けたときに,その経費を事業者・施設に支払いますが,支払う経費に対し市町村が支援費を支給することになります.サービス提供を希望する者は市町村に申請し,市町村が支給を行うことが適切と認めるときに支給の決定をします.決定後に指定業者・施設と契約し,サービスを利用することができます.指定業者・施設は市町村に支援費を請求して代理受領することになります.
支援費制度において対象となるサービスは,身体および知的障害者の施設訓練等支援または居宅生活支援,障害児の居宅生活支援です.
2. 支給決定について
支給にあたっては,市町村は障害の種類・程度・その他の心身の状況,介護を行う者の状況など8項目の内容を勘案して,その要否を決定します.さらに,施設訓練等支援費であれば障害程度区分と支給期間を,居宅生活支援費であれば支給量と支給期間を定めることになります.
3. 障害程度区分について
身体および知的障害者施設の入所者は,それぞれの障害程度によってA,B,Cに3区分されます.区分は施設種別毎に設定されているチェック項目について,市町村が聞き取りを行って決めます.各施設におけるチェック項目は,支援の態様や必要とする頻度等により選択肢が3つずつ設定されています.選択肢に支援の必要性の大きい順に2点,1点,0点を与え合計点数を出し,その合計点によって対応する区分が決まります.例えば,身体障害者更生施設入所を希望する者が20点であれば,区分Bになります(区分は25点以上がA,24点以下11点以上がB,10点以下がCです).
市町村レベルで障害程度区分ができない場合には更生相談所の専門的判定を求めることができます.
4. 支援費の基準
支援費は,厚生労働大臣が定めた基準を下回らない範囲内で市町村長が定めることになります.国の基本的な考えとしては,①障害程度区分及び施設規模に応じて単価に格差をつける,②加算措置はできるだけ包括化して,施設等の自主的な経営努力を促す,③障害者の地域生活の推進を評価する,④サービスに要する費用として新たに減価消却費を見込む等を挙げています.2002年9月に支援費の基準額の案が出されました.身体障害者療護施設の支援費単価を例にとると,標準規模(41~90人)では区分Aが393,200円,区分Bが373,500円,区分Cが353,800円となりますが,小規模施設では高くなり,大規模施設では低くなります.これに地域生活移行努力を評価する入院および退院特別加算費,ALS等の障害特性を配慮した加算費が加わります.
一方,居宅生活支援としてのデイサービス事業およびショートステイ事業においても,必要とする支援の程度によって3区分の単価が設定されています.
5. 支援費制度における医師の役割
(1) 主治医として,福祉制度利用に関する情報提供:障害者の福祉制度は一般臨床の延長上にあります.主治医は患者・障害者に対して支援費制度の情報を提供し,それを利用できるように助言・援助することにより,患者さんの社会への再定住に役立てることができます.
(2) 市町村からの問合せに対する意見書,診断書の作成:市町村が支援費給付を決定する際,「その他の心身の状況」を勘案することになりますが,その際,主治医に問合せをするほか,健康診断書を求めることがあります.更生相談所の医師の判定を経ないで入所(支援費給付)の適否が決まるので,主治医の意見や診断書の重みが増すことになります.
(3) サービス提供指定事業者・施設の運営:身体障害者更生援護施設の設置・運営基準によると,入所者の健康管理や療養上の指導を行うために医師を配置する規定があります.特別の障害特性を有する者への対応として,身体障害者更生施設,身体障害者療護施設に常勤の医師を配置した場合に加算されます.さらに,身体障害者療護施設にALS等の障害者が入所している場合,神経内科医を配置すれば加算されます.施設が障害者に選ばれる時代になろうとしています.施設の評価は医師の存在の有無によっても大きく影響されるので,事業者は常勤医の配置を考え,障害者に質の高いサービスを提供するものと思います.これまで以上に障害者にかかわる医師が必要になるでしょう.
(佐々木鐵人,委員長 山口 明)
(リハニュース16号:2003年1月15日)
今年4月1日から障害者福祉サービス提供の仕組みが変わり,支援費制度がスタートします.以下に,この制度のアウトラインを述べます.
1. 支援費制度が目指すもの
全く新しい制度ができるのではなく,行政がサービスの受け手を特定し,サービスの内容を決定するという措置制度から支援費制度に移行いたします.支援費制度とは障害者の自己決定および利用者本位のサービス提供を尊重する制度です.障害者自ら事業者・施設との対等な立場で,サービスを選択し,契約する仕組みになります.
利用者は事業者・施設からサービスの提供を受けたときに,その経費を事業者・施設に支払いますが,支払う経費に対し市町村が支援費を支給することになります.サービス提供を希望する者は市町村に申請し,市町村が支給を行うことが適切と認めるときに支給の決定をします.決定後に指定業者・施設と契約し,サービスを利用することができます.指定業者・施設は市町村に支援費を請求して代理受領することになります.
支援費制度において対象となるサービスは,身体および知的障害者の施設訓練等支援または居宅生活支援,障害児の居宅生活支援です.
2. 支給決定について
支給にあたっては,市町村は障害の種類・程度・その他の心身の状況,介護を行う者の状況など8項目の内容を勘案して,その要否を決定します.さらに,施設訓練等支援費であれば障害程度区分と支給期間を,居宅生活支援費であれば支給量と支給期間を定めることになります.
3. 障害程度区分について
身体および知的障害者施設の入所者は,それぞれの障害程度によってA,B,Cに3区分されます.区分は施設種別毎に設定されているチェック項目について,市町村が聞き取りを行って決めます.各施設におけるチェック項目は,支援の態様や必要とする頻度等により選択肢が3つずつ設定されています.選択肢に支援の必要性の大きい順に2点,1点,0点を与え合計点数を出し,その合計点によって対応する区分が決まります.例えば,身体障害者更生施設入所を希望する者が20点であれば,区分Bになります(区分は25点以上がA,24点以下11点以上がB,10点以下がCです).
市町村レベルで障害程度区分ができない場合には更生相談所の専門的判定を求めることができます.
4. 支援費の基準
支援費は,厚生労働大臣が定めた基準を下回らない範囲内で市町村長が定めることになります.国の基本的な考えとしては,①障害程度区分及び施設規模に応じて単価に格差をつける,②加算措置はできるだけ包括化して,施設等の自主的な経営努力を促す,③障害者の地域生活の推進を評価する,④サービスに要する費用として新たに減価消却費を見込む等を挙げています.2002年9月に支援費の基準額の案が出されました.身体障害者療護施設の支援費単価を例にとると,標準規模(41~90人)では区分Aが393,200円,区分Bが373,500円,区分Cが353,800円となりますが,小規模施設では高くなり,大規模施設では低くなります.これに地域生活移行努力を評価する入院および退院特別加算費,ALS等の障害特性を配慮した加算費が加わります.
一方,居宅生活支援としてのデイサービス事業およびショートステイ事業においても,必要とする支援の程度によって3区分の単価が設定されています.
5. 支援費制度における医師の役割
(1) 主治医として,福祉制度利用に関する情報提供:障害者の福祉制度は一般臨床の延長上にあります.主治医は患者・障害者に対して支援費制度の情報を提供し,それを利用できるように助言・援助することにより,患者さんの社会への再定住に役立てることができます.
(2) 市町村からの問合せに対する意見書,診断書の作成:市町村が支援費給付を決定する際,「その他の心身の状況」を勘案することになりますが,その際,主治医に問合せをするほか,健康診断書を求めることがあります.更生相談所の医師の判定を経ないで入所(支援費給付)の適否が決まるので,主治医の意見や診断書の重みが増すことになります.
(3) サービス提供指定事業者・施設の運営:身体障害者更生援護施設の設置・運営基準によると,入所者の健康管理や療養上の指導を行うために医師を配置する規定があります.特別の障害特性を有する者への対応として,身体障害者更生施設,身体障害者療護施設に常勤の医師を配置した場合に加算されます.さらに,身体障害者療護施設にALS等の障害者が入所している場合,神経内科医を配置すれば加算されます.施設が障害者に選ばれる時代になろうとしています.施設の評価は医師の存在の有無によっても大きく影響されるので,事業者は常勤医の配置を考え,障害者に質の高いサービスを提供するものと思います.これまで以上に障害者にかかわる医師が必要になるでしょう.
(佐々木鐵人,委員長 山口 明)
(リハニュース16号:2003年1月15日)