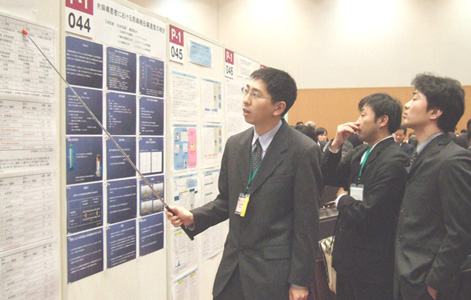 第35 回日本臨床神経生理学会学術大会が、満留明久大会長(福岡大学医学部小児科学教室主任教授)のもと、2005 年11 月30 日〜 12 月2 日の3日間にわたって福岡国際会議場で開催されました。
第35 回日本臨床神経生理学会学術大会が、満留明久大会長(福岡大学医学部小児科学教室主任教授)のもと、2005 年11 月30 日〜 12 月2 日の3日間にわたって福岡国際会議場で開催されました。本学会は、2000 年に「日本脳波・筋電図学会」から「日本臨床神経生理学会」に名称が変わりました。今回の学術大会においても、脳波、筋電図に加え、磁気刺激、脳機能イメージング、認知機能についての神経生理学的研究など、発表領域は多岐にわたりました。プログラムは非常に内容の濃い構成であり、会場は予定表を片手に移動する多くの参加者で賑わいました。
12 題の教育講演や11 のシンポジウムでは、基礎的な事柄から最近の話題まで、幅広い内容が扱われ、ワークショップやハンズオンセミナーでは、臨床に即した、実際の検査手技についての講習や症例検討が行われました。特別講演では、Peter Brown 先生(UCL)がパーキンソン病におけるbasal ganglia-cortical loop についてβ バンド活動の同期を中心に、長谷川寿一先生( 東京大学) が進化心理学と臨床神経生理学の連携について、Guillermo Paradiso 先生(Toronto Western Hospital)が腰仙髄の術中神経生理学的モニタリングについて、それぞれ貴重な講演をしてくださいました。
一般演題では、ポスター発表、口演とも、基礎・臨床医学両面において多くの興味深い発表がなされ、活発な討論が繰り広げられました。中には、香りや音楽、飲酒、足湯など、日常的な事柄が生体に及ぼす影響を神経生理学的に分析したユニークな発表もありました。討論の中では、鋭い質疑応答のみならず、今後の研究発展に寄与するコメントも多く交わされ、当学会やそれぞれの専門領域を盛り上げていこうという機運が感じられました。
次回の第36 回学術大会は、2006年11 月29 日から12 月1 日まで、神奈川県のパシフィコ横浜で開催される予定です。神経生理学はリハビリテーション医学において、生体機能や障害の機序を明らかにする研究はもちろんのこと、機能障害の評価、治療効果判定などの客観的指標として、非常に重要な分野です。また、今回の大会でも周知されたように、2006 年より当学会による認定医・認定技術師の移行措置による認定が開始され、より一層の発展が期待されます。次回も、より多くの皆様に参加をお勧めします。
(リハニュース28号:2006年1月15日)