| 医学生リハセミナーに参加して | 春期・GW |
日本リハ医学会 医学生リハセミナーに参加して
春期:昭和大学
4年生
このたび、平成18年医学生リハセミナーに参加し、昭和大学リハ医学診療科を訪れる機会を得ました。旭川医科大学には単独でリハ科が設けられておらず、また、今後の高齢化に伴いますます重要性を増すリハの現場を知るよい機会と思い応募しました。
セミナーのプログラムは、カンファレンス、病棟回診、リハセンター見学、リハについての講義などでした。カンファレンスでは、医師のみならず理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、看護師などのさまざまな職種の方々が、積極的に参加されていました。このことから、リハにおいては、チーム医療、連携が特に重要であること、また、単にADL(日常生活動作)の回復といったこと以上にさまざまな配慮が必要であることを学びました。病棟回診では、リハ医学診療科の対象が予想以上に多くの部門にわたっていたのが印象的でした。患者さんに対しては、それぞれに応じてきめ細やかに声をかけられ、また、時には患者さんに納得のいくまで話をしてもらう様子を見学しました。リハセンターでは、理学療法、作業療法の様子を垣間見ることができました。また、自分は松葉杖の使い方ひとつにしても知らなかったことを知り、臨床の難しさを実感しました。嚥下外来、ビデオ嚥下造影検査の見学では、内視鏡や造影検査の実際を学びました。最後に、水間教授から、症例やリハにおけるチームと連携の考え方、医療が「治療・予防・リハ」の3つの柱から成り立っていることを説明していただきました。
当初、リハは整形外科の一分野というイメージをもっていました。実際に見学させていただくと、耳鼻科、循環器・呼吸器・消化器内科、神経内科、産婦人科、小児科、心臓外科、脳外科等多くの領域の患者さんに関わっていることがわかりました。特定の臓器、疾患ではなく全身を対象としていること、急性期、回復期などさまざまなステージで、長期にわたり患者さんと関わりをもつことは、難しさと同時にやりがいも感じられるものではないかと思います。昭和大学のリハ医学診療科では、臨床を重視しつつ、教育、研究にも配慮がされているようでした。
セミナー当日は、ちょうど春の異動の時期にあたり、科内の送別会にも参加させていただきました。参加者の方々の挨拶や交流などから、それぞれの職種を超えたアットホームな雰囲気や、これからのリハを開拓、支えていこうという意欲が感じられました。
今回、こうした機会を与えていただきました水間正澄教授をはじめ昭和大学リハ医学診療科の皆様には大変お世話になりました。この場を借りて御礼申し上げます。
春期:広島大学
5年生
3月下旬の木・金曜日の2日間、広島大学病院リハ部で実習しました。主に、紹介された入院患者さんを訪室しリハ計画を立てることに同行したり、外来・カンファレンス・施設見学などをしました。
リハ計画を立てるために問診したり所見をとるとき、先生は職業や退院後のことに加え、趣味や好きなことも聞いていました。ただ単調な動作や作業をこなすのではなく、楽しみながらやれて今後の生活にいかせるように配慮しているそうです。その計画に基づいて、具体的にどんな動作をどれだけ行うのか決めるのはPT・OTの先生方です。標準的なリハ例もあるそうですが、患者さんの状態や興味などに応じて日々工夫して行っているそうです。リハは一人では行えず、さまざまな職種のスタッフが協力して行います。
全員が揃ったカンファレンスで患者さん一人ひとりについて話し合っていました。この実習で一番印象に残ったことは、スタッフ皆さんの仲がとても良く雰囲気がよかったということです。普段からお互い意見を交換しやすいこともリハにおいてとても重要だと感じました。
先生方には、今後の進路のことや研修でどの科を学んできたらよいかなど相談にのっていただき、また、先生方の行っている取り組みや広島の今後のリハ医療の展望を聞かせていただきました。今回私は就職先を決めるための病院見学を兼ねていたので、将来をイメージでき、リハの扱う範囲がますます広がっていくことに興味がわき、今後自分もリハに携わっていきたいという決意が固まりました。
お忙しい中を時間を割いてくださっていろんなお話を聞かせていただき、とてもお世話になりました。本当にありがとうございました。
春期:高知大学
4年生
私は元々リハの仕事がしたくて医学部を選んだのですが、大学ではいろいろな科の勉強をするため、最近ではリハに対する興味が薄れてきていました。しかし、今回見学させていただいて、やはり自分はこういう仕事がしたいのだとあらためて思いました。それと同時に、それぞれのスタッフの役割や仕事に対するイメージが変わりました。
医師がいろいろな科に入院している患者さんに対しても、詳しく問診しているのに驚きました。そういったことは既に終わってリハに関することだけを担当するのかと思っていました。糖尿病の患者さんに、神経症だけでなく目や腎臓のことも尋ね、丁寧に説明している場面や、脳梗塞のリハにこられた患者さんに、認知症のテストをしている場面が特に印象に残っています。
今考えると、医師ですから患者さんの全体を把握するのは当然のことで、私も分かっているつもりでしたが、実際は分かっているつもりになっていただけでした。今後はいろいろな病気や症状を勉強するとき、単独でなく互いに結びつけながら考えるようにしていこうと思います。またこのような機会があったらぜひ参加させてください。2日間ありがとうございました。
○
4年生
これまで付属病院のリハ部に入ったこともなく、リハの実際を知らないどころか文章ですらあまり読んだことはなかった私でしたが、リハの現場をみせていただけるとあって、強い好奇心を覚えて応募しました。
2日間の日程で、PT・OTや言語聴覚士(ST)の方に職務内容について教えていただいたり、医師の診察を見学させていただいたりしました。そして、リハという医療は、多くの専門家によって行われていることや、リハの対象となる疾患は整形外科のものだけではなく外科や内科など多岐にわたっていることを知りました。また、何人かの患者さんとお話しすることができたのですが、もっとも印象に残ったのは部屋の雰囲気が全体的に明るいことでした。部屋の採光やBGMの影響もあると思いますが、私が強く感じたのは患者さんたちの口調や表情の明るさでした。先生が「リハはまずゴールありきだ」とおっしゃっていましたが、定めた目標に向かって努力している充実感が患者さんたちから感じられました。今回医療の現場を見せていただいて、「リハ」という医療のあり方の一部を知ることができました。いろいろ教えてくださった先生やスタッフの皆様に感謝いたします。
春期:北海道大学
5年生
自分の大学ではリハ科の講義や実習が全くありません。そのためリハに関しては以前から興味はあったのですが、接することができずに6年生になってしまい、ゆっくり見学できる最後のチャンスかと思い、参加しました。
リハは自分にとっては、PTやOTがやる整形外科的なイメージが強かったのですが、今回参加してイメージがかなり変わりました。神経内科の多系統萎縮症から、脳神経外科的な交通外傷後による高次脳機能障害などまで幅広く、治療方法に関しても磁気刺激やフェノールなどによるブロック療法など多種にわたっていました。また、医師だけでなく PT・OT・看護師などたくさんの職種による密接なチーム医療を行っていく科は 今までの病院実習では経験したことがなく、非常に新鮮でした。リハ医はこれからの高齢化社会、医療技術の進歩による患者の増加が予想され、より必要となってくると思います。その上、複雑な疾患の合併例も多く、医師の専門性も高くなっていくでしょう。需要も高く将来性もあり、やりがいのある科だと思うので、将来の選択肢の1つとして考えてみたいと思います。3日間ありがとうございました。
○
4年生
3日間大変興味深い実習をさせていただき、誠にありがとうございました。いろいろな疑問点に関しても質問ができ、リハの新たな一面が見られたことは本当に将来どのような進路を選択するかに関していろいろと考える所がありました。
すごくびっくりしたのは、リハの専門性の高さと行っているリハの分野が初めて見る神経内科の分野が中心という点でした。ほとんど運動器リハがありませんで、自分はリハというと脳血管障害か運動器疾患が半分以上を占めるという認識でしたので、非常に驚きました。
【頭部外傷】での『ほとんど機能する脳が少ない』症例において、『何の機能が残っているのか』という【慎重な検査の必要性】を感じました。本当に検査の種類が多く、その内容に関してもかなり高度だったので、どんどん進化していて、多様になっているのだと感じました。
北大のリハでハードの面でも本当に驚きました。今まで見て来たリハ施設のほとんどがそろっていて、宝の山に見えました。それが人不足でまわしきれていない感がありました。
リハ医がもっと増える、スタッフがもっと増えることにより、ここでいろいろな研究が可能であり、きっとこれからの成長が未知数ではないかと感じました。床反力計があり、歩行解析ができる点も感動しました。自分は足首に特に興味があって、こんなに広い面積で解析できて設備が立派であることに感動してしまいました。
今回時間は少なかったのですが、OT、PTの方からのお話を聞くことができたのも収穫だったと思います。ただ、実際に患者さんと接していてリハをしている場面を見ておきたかったという希望はありました。
それぞれの職種でできる限り多い時間をカンファレンスに使っていたため、患者さんにとってはさまざまな角度からの評価が得られ、医療スタッフでも疑問点を共有しやすいのではないかと感じました。
大変ご多忙の中、先生皆様には非常に有益なご教授をいただき、とても身になりました。いろいろな要望もさせていただき、ご迷惑もおかけしました。厚くお礼申し上げます。
春期:聖隷三方原病院
リハセミナーの実習報告書が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。こちらは昨日から大学病院の実習が始まりました。最初の2週間は呼吸器・循環器・小児外科の配属で、明日は手術の現場を見学させてもらう予定です。
今回の春季リハセミナーは2日間だけでしたが、リハ科の皆様方に暖かく迎え入れていただき、外来、嚥下リハ、理学療法などを中心に見学させていただきました。
外来ではどの患者さんも以前より症状が改善してきている様子に、また嚥下リハでは他の病院では嚥下が不可能とされた患者さんでもこの病院に来て嚥下が可能になった例を見ることができ、大変感銘を受けました。
普通の人々が当たり前のように行っている動作が、ある日突然事故や病気のために行えなくなるというのはとてもショックなことであり、リハを通して以前の動作あるいは体の別の部位や器具を使ってそれに相当する動作を獲得することの困難さ、そしてそれらを獲得するために日々進歩する患者さんの喜びを感じ取ることができました。
理学療法の現場では、患者さんの簡単なサポートをさせていただいたり、患者さんやスタッフの皆さんと会話することで楽しい時間を過ごさせていただきました。
また、片桐先生の講義では、将来医師となったときに必要な心構えについてご教授いただきました。実習が終わってからは藤島先生にテニスに誘っていただいたり、我々実習生のために親睦会を開いていただいたことについても大変感謝しております。
今回の実習は、今後医師を目指していく上で非常に貴重な体験をさせていただいたと思っておりますが、まだほかにも学ばせていただくべきことがたくさんあることと思いますので、機会がありましたらまたお邪魔させていただきたいと考えております。大変お世話になり本当にありがとうございました。
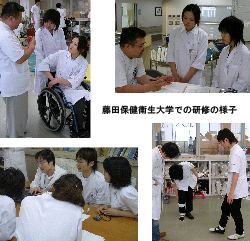
GW:藤田保健衛生大学
3年生
今回セミナーに参加して、装具をつけて少し足の不自由さがわかりました。また、今まで装具は安定させるためだけだと思っていたのですが、難易度を下げるためというのが意外でした。セミナーで行ったような咽頭内視鏡検査や筋電図などの実習はふだん授業でできないので勉強になりました。
全体的な感想として、実習で見た内視鏡の映像は、授業のスライドや教科書ではよくわからないところだったのでとてもよかったです。また、リハ医の存在は知っていましたが内容を知りませんでした。訓練のプログラムを計画したり、患者さんの状態を診て薬や食事を決める、PT、OTなどをまとめるという仕事があることがよくわかりました。ありがとうございました。
日本リハ医学会教育委員会
医学生リハセミナー担当 中馬孝容