第33回国際福祉機器展
日本リハビリテーション医学会広報委員会 大高洋平
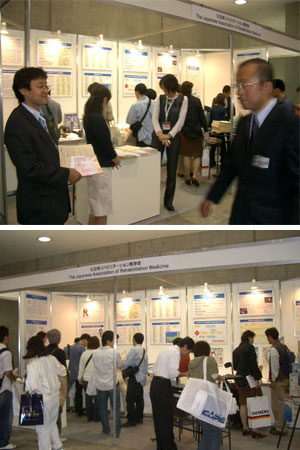 第33回国際福祉機器展が2006年9月27日から3日間、東京ビッグサイトで開催されました。日本リハ医学会は、広報活動の一環として、3年前より展示ブースを出展し、リハ医療、リハ医学会の活動を一般の方々に広く知っていただくことを主目的として企画、展示を行ってまいりました。2006年も前年同様に、2ブースを利用してのパネル展示を行い、「リハ科専門医の都道府県別名簿」や、会員のみなさまからご応募いただいた「リハ科医が関わる福祉機器開発」一覧表なども配布しました。また、今年度より、新しい試みとして学会ホームページ(市民のページ)に掲載している「主な疾患のリハビリテーション」を小冊子にまとめ無料で配布し、リハ医療を広く市民の方に広報いたしました。ブースは例年以上に賑わい、リハ医療に対する興味・期待の大きさを改めて感じさせられ、今後の広報活動の重要性を強く再認識させられました。
第33回国際福祉機器展が2006年9月27日から3日間、東京ビッグサイトで開催されました。日本リハ医学会は、広報活動の一環として、3年前より展示ブースを出展し、リハ医療、リハ医学会の活動を一般の方々に広く知っていただくことを主目的として企画、展示を行ってまいりました。2006年も前年同様に、2ブースを利用してのパネル展示を行い、「リハ科専門医の都道府県別名簿」や、会員のみなさまからご応募いただいた「リハ科医が関わる福祉機器開発」一覧表なども配布しました。また、今年度より、新しい試みとして学会ホームページ(市民のページ)に掲載している「主な疾患のリハビリテーション」を小冊子にまとめ無料で配布し、リハ医療を広く市民の方に広報いたしました。ブースは例年以上に賑わい、リハ医療に対する興味・期待の大きさを改めて感じさせられ、今後の広報活動の重要性を強く再認識させられました。
※国際福祉機器展に関する詳しい情報は、国際福祉機器展のweb site : http://www.hcr.or.jp/でご覧ください。
※展示会にご協力いただいた以下の会員の先生方に深く御礼申し上げます。
松井彩乃先生(埼玉医科大学総合医療センター)、関聰介先生(川崎医科大学リハ医学教室)、杉原勝宣先生(土浦協同病院リハ科)、米田千賀子先生(藤田保健衛生大学医学部リハ医学講座)、山中崇先生(川崎医科大学リハ医学教室)、岡崎英人先生(藤田保健衛生大学病院七栗サナトリウム)、土田敏典先生(恵寿総合病院整形外科)
第22回日本義肢装具学会学術大会
運営委員長(熊本機能病院) 山永裕明
心部に位置する鶴屋百貨店鶴屋ホール・くまもと県民交流館パレアにて第22回日本義肢装具学会学術大会が、米満弘之会長(医療法人寿量会熊本機能病院理事長)のもとで開催されました。
超高齢社会を迎えるに当たり、高齢者の疾病、障害における治療および生活機能の低下予防における義肢装具の果たす役割の重要性から、「高齢社会と義肢装具」を大会テーマに掲げました。
学術大会前日には市民公開講座を開催し、「人生賛歌両腕を失って」をテーマに不慮の事故で両腕を失った大野勝彦氏と澤村誠志先生、米満弘之会長による鼎談を行い、会場もほぼ満席状況で大いに盛り上がり市民の皆さんに楽しんでいただきました。以下学術大会の概要を報告いたします。
会長講演として「高齢者の整形外科的疾患と義肢装具」、招待講演はオーストラリアのラトローブ大学マイケルディロン先生に「坐骨収納型ソケットのコンセプトの再評価」についてお話いただきました。特別講演は「ユニバーサル社会への道標」 「義肢装具教育の国際的な動向と、発展途上国における国際援助活動の近況」の2題、パネルディスカッションとして「高齢高位下肢切断者と義足−地域での使用実態とメンテナンスの実際−」 「チーム医療における義肢装具士のあり方−現状と課題」の2題、シンポジウムとして「脳卒中の短下肢装具−病態によるベストの選択」 「義肢・装具材料の最近の進歩」の2題、教育講演は「カーボン装具の有用性」を始めとして6題、早朝レクチャー2題、また一般口演74題、ポスター演題21題。この大会の特徴である商業展示も、マニュファクチャラーズワークショップもそれぞれ30社、6社の出展がありました。
本大会は参加者が熱心でどの会場も参加者でにぎわい、特に早朝レクチャーは朝が早いので出足が心配されましたが、立ち見が出るほどの盛況でした。地方都市での開催にもかかわらず参加者が1,000名を超え無事閉会しました。
第36回日本臨床神経生理学会学術大会
慶應義塾大学リハビリテーション医学教室補永薫
第36回日本臨床神経生理学会学術大会が、黒岩義之会長(横浜市立大学大学院・神経内科学部門教授)のもと、2006年11月29日〜12月1日の3日間にわたりパシフィコ横浜で開催されました。本学会では学術大会においても、脳波、筋電図に加え、磁気刺激、脳機能イメージング、認知機能についての神経生理学的研究など多岐にわたる発表がなされました。
44題の教育講演や17のシンポジウムでは、基礎的な事柄から最近の話題まで、幅広い内容が扱われ、ワークショップやハンズオンセミナーでは、臨床に即した、実際の検査手技についての講習や症例検討が行われ、会場は予定表を片手に移動する多くの参加者で賑わいました。特別講演では、Gastone G. Celesia先生(Loyola University)が最近の視覚誘発電位(VEP)の知見を中心に、Zsolt Garami先生(University of Texas-Hauston)が脳卒中急性期における経頭蓋ドップラーエコーの有用性について、それぞれ貴重な講演をしてくださいました。
一般演題では、基礎・臨床医学両面において多くの興味深いポスター発表がなされ、活発な討論が繰り広げられました。討論の中では、鋭い質疑応答のみならず、今後の研究発展に寄与するコメントも多く交わされ、当学会やそれぞれの専門領域を盛り上げていこうという機運が感じられました。
次回の第37回学術大会は、2007年11月21日から23日まで、栃木県総合文化センターで開催される予定です。神経生理学はリハ医学において、生体機能や障害の機序を明らかにする研究はもちろんのこと、機能障害の評価、治療効果判定などの客観的指標として、非常に重要な分野です。次回も、より多くの皆様に参加をお勧めします。
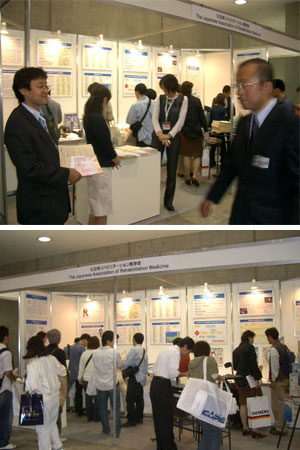 第33回国際福祉機器展が2006年9月27日から3日間、東京ビッグサイトで開催されました。日本リハ医学会は、広報活動の一環として、3年前より展示ブースを出展し、リハ医療、リハ医学会の活動を一般の方々に広く知っていただくことを主目的として企画、展示を行ってまいりました。2006年も前年同様に、2ブースを利用してのパネル展示を行い、「リハ科専門医の都道府県別名簿」や、会員のみなさまからご応募いただいた「リハ科医が関わる福祉機器開発」一覧表なども配布しました。また、今年度より、新しい試みとして学会ホームページ(市民のページ)に掲載している「主な疾患のリハビリテーション」を小冊子にまとめ無料で配布し、リハ医療を広く市民の方に広報いたしました。ブースは例年以上に賑わい、リハ医療に対する興味・期待の大きさを改めて感じさせられ、今後の広報活動の重要性を強く再認識させられました。
第33回国際福祉機器展が2006年9月27日から3日間、東京ビッグサイトで開催されました。日本リハ医学会は、広報活動の一環として、3年前より展示ブースを出展し、リハ医療、リハ医学会の活動を一般の方々に広く知っていただくことを主目的として企画、展示を行ってまいりました。2006年も前年同様に、2ブースを利用してのパネル展示を行い、「リハ科専門医の都道府県別名簿」や、会員のみなさまからご応募いただいた「リハ科医が関わる福祉機器開発」一覧表なども配布しました。また、今年度より、新しい試みとして学会ホームページ(市民のページ)に掲載している「主な疾患のリハビリテーション」を小冊子にまとめ無料で配布し、リハ医療を広く市民の方に広報いたしました。ブースは例年以上に賑わい、リハ医療に対する興味・期待の大きさを改めて感じさせられ、今後の広報活動の重要性を強く再認識させられました。